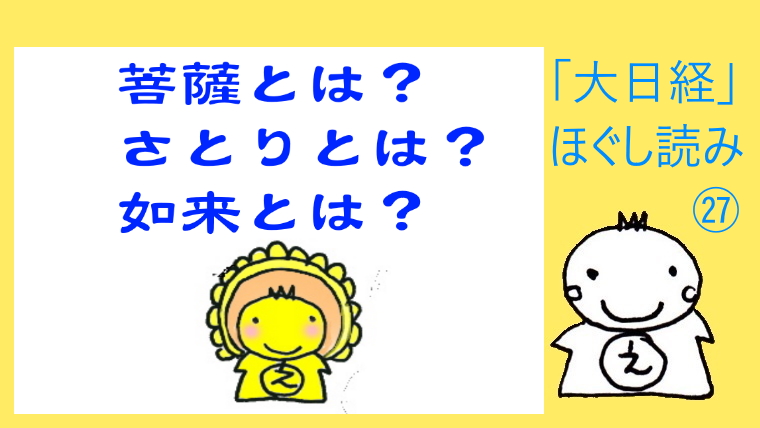この「大日経」(だいにちきょう)説如来品第二十六(せつにょらいぼん)は、角川文庫「全品現代語訳 大日経」著者:大角修先生の本を主に参考にして、ほぐし読みにしました。
前回、大日如来は、「三つの心の三昧耶」を説かれました!

菩薩とは?さとりとは?如来とは? 説如来品第二十六「大日経」
説如来品第二十六(せつにょらいぼん)
金剛薩埵は大日如来に質問をします。
※下記に補足あります。
①何を菩薩とよび、②何が正覚のさとりなのでしょうか?
③何を如来とし、何が世尊とされるのでしょうか?
大日如来は大乗の仏道を説いて回答しました。
菩提であるさとりは、虚空の相にして一切の分別を離れているのです。
①その「さとりの菩提を求める者」を菩提薩埵(ぼだいさった)と名付けるのです。
十地(じゅうじ)を成就し、
よく自在に諸法は空にして幻のごとくと通達し、
一切は同じと知り、
②諸々の世間の趣(しゅ・境涯)を解くことを正覚と名付けます。
法は虚空の相のごとく、無二にして、ただ一相なのです。
仏の十智力(じゅうちりき・いろいろな智慧の力)を成就することを三菩提(さんぼだい・サムボーディ=正智)と名付けます。
智慧をもって無明をやぶるのです。
自性(智慧そのものである本性)は言説を離れ、言葉では表せないのです。
③自証の智慧なので、それを名付けて如来というのです。
《説如来品第二十六 おわり》 つづく
※最初の金剛薩埵の質問の順番は、大日如来の回答の順番が逆のため入れ替えています。
十地(じゅうじ)について
十地(じゅうじ)は「菩薩の修行52段階」の41段階から50段階の事です。
こちらに表があります。↓



如来(にょらい)について
如来 (にょらい)は、サンスクリットで「タターガタ」
「如」は、「真実から現れた」
「来」は、「者」と
原始仏典第一経「梵網経」に解説があります。
第十六経「大般涅槃経」の中村元先生の解説も載せておきます。
「タターガタ」(tathāgata)とは本来、「そのように行きし者」「あのように立派な行いをした人」という語義であり、仏教・ジャイナ教・その他の古代インド当時の諸宗教全般で「修行完成者」つまり「悟りを開き、真理に達した者」を意味した語であるが、
「如来」という漢訳表現には「人々を救うためにかくのごとく来たりし者」という後世の大乗仏教的な見解がひそんでいて、初期仏教における語義とは乖離(かいり)があると解説されています。
原始仏典第十六経「大般涅槃経」解説より
ねぇ、ぼーさん!「大日経」さとりは、虚空の相にして一切の分別を離れているんだね。
えん坊!ほんとだね!
最初に「身語意平等の法門が開かれた」って言っているからね。
第一品を見直してから、つづきも見てみよう!
第一品「入真言門往心第一」より抜粋
空性(空の本性)は姿かたちがないので、
六根(眼耳鼻舌身意)で知覚できなく言論を超えたところにあるのです。
空性で生じ尽きることない、
有為(うい・流転する迷いの世界)と、
無為(むい・迷いがなくなった世界)の界を離れ、
六根を離れ極無自性心(自己の実体を固定的に見ない心の極み)の仏法が生じるのです。
これが、成仏の因(さとりのもと)
と大日如来は教説しています。
《合わせて読んでみて》
平等の法門も解説しています。↓



参考文献↓