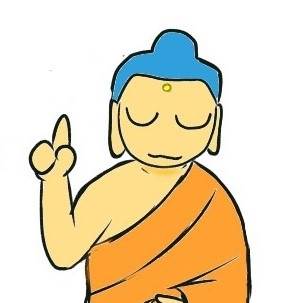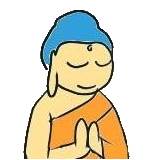原始仏典 中部経典 第147経「教羅睺羅小経」(きょうらふらしょうきょう)「ラーフラの解脱」は、ブッダがラーフラに解脱をさせるお経です。読みやすくほぐして、さらにブッダの教えもわかりやすくしています。
第61経、第62経と合わせてお読みください!


ブッダがラーフラを解脱させるお経 中部経典 第147経 「教羅睺羅小経」(きょうらふらしょうきょう)ラーフラの解脱
わたしはこのように聞きました!キラキラ♪
ブッダが一人で瞑想していたときに、
心の中にこのような思いが浮かびました。
ラーフラのなかで、
解脱をもたらすものは、もう成熟した。
わたしはラーフラが煩悩を滅尽するように、
かれをさらに指導することにしよう。
瞑想を終えて、托鉢もすましてから、
ブッダはラーフラに声をかけました。
ラーフラよ、坐具を取りなさい。アンダ林に行こう。
ラーフラは坐具を持って、
ブッダについていきました。
その時、
数千の神々も、
今日、尊師は、
ラーフラが煩悩を滅尽するよう、
さらにかれを指導するでしょう!
と考えて、
世尊の後についていきました。
そして、
ブッダとラーフラは樹に座り、
ブッダはラーフラに問いかけていきました。


《六根の眼耳鼻舌身意に関する無常・苦・無我の教え》
ラーフラよ、
これをどのように考えるのか?
眼は常住であるか、これとも無常であるか?
無常です。
では、無常であるものは苦であるか、楽であるか?
苦です。
では、無常であり、苦であり、変化する性質のものを、
『これはわたしのものである、これはわたしである、これはわたしの自我である』
とみなすことは正しいであろうか?
それは正しくありません。
それと同様に、
《眼に関する無常・苦・無我》
色かたちの「色」
眼でみて認識する「眼識」
眼における接触の「眼触」
眼における接触によって生じる「感受」
表象の「想」
意志の「行」
意識の「識」
これらも
無常であり、苦であり、変化する性質のもので、
『これはわたしのものである、これはわたしである、これはわたしの自我である』
とみなすことは正しいであろうか?
それは正しくありません。
次に、「耳」に関する無常・苦・無我を
ブッダは説きます。
《耳に関する無常・苦・無我》
音声の「声」
耳で聞いて認識する「耳識」
耳における接触の「耳触」
耳における接触によって生じる「感受」
表象の「想」
意志の「行」
意識の「識」
これらも
無常であり、苦であり、変化する性質のもので、
『これはわたしのものである、これはわたしである、これはわたしの自我である』
とみなすことは正しいであろうか?
それは正しくありません。
ブッダは、ラーフラに
六根の眼・耳につづき、鼻・舌・身体・意も同様に、
無常・苦・無我の確認をひとつひとつしていきます。
そして、
ブッダはラーフラに、
厭離(おんり)することで、解脱することを説いていきます。
《厭離から解脱》
ラーフラよ、よく聞いて学んだ聖者の弟子は、
そのように見ていくので、
眼を、厭(いと)い離れ、
色かたちを、
視覚的認識を、
眼における接触を、
眼における接触によって生じる感受を、
表象を、
意志を、
意識をも厭い離れるのです。
また、
耳を厭い離れ、
音声を、聴覚的認識を、耳における接触を、
耳における接触によって生じる感受を、
表象を、
意志を、
意識をも厭い離れるのです。
ブッダはさらにラーフラに、
六根の眼・耳につづき、
鼻・舌・身体・意も同様に、
『厭い離れる』(いといはなれる)ことを説きます。
ブッダの説法は続きます。
かれは、
厭い離れるので、貪りを離れる。
貪りを離れることにより解脱する。
そして、
解脱したとき「解脱した」という知が生まれ、
『再び生まれることはなくなった。清らかな修行(梵行)は完成した。なすべきことはなし終えた。さらにこのような迷いの生存にいたることはない』
と知るのです。
ブッダは
以上のように
ラーフラに説法をしました。
すると、
ラーフラは世尊の説かれたことに歓喜しました。
《真理を見る眼》
この解脱が説かれているとき、
ラーフラ尊者の心は、執着がなくなって、
もろもろの煩悩から解脱した。
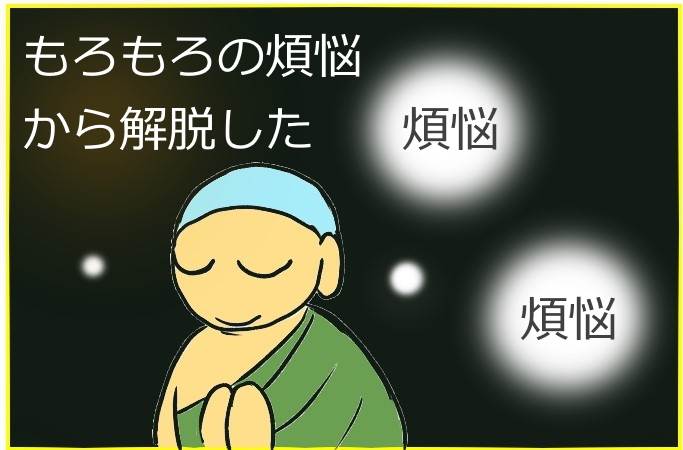
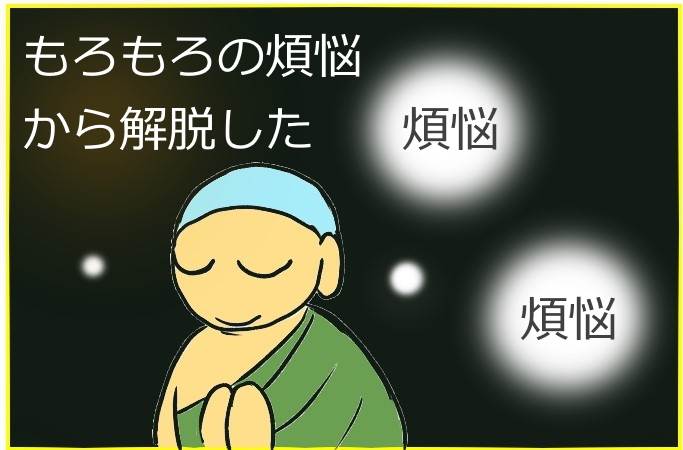
解脱できました。ふふふ♪
そして、
そこにいた数千の神々には、
塵を離れ、
垢を離れた真理を見る眼(法眼)が生じました。
それは、
どんなものであろうと、
生起するものは、
すべて消滅するものである
というものである。


《中部経典 第147経 「教羅睺羅小経」ラーフラの解脱》「完」
ぼーさん!
ラーフラさん、ついに解脱したんだね!すごいね!
ほんとすごいよね!えん坊!
ブッダの教えで、きちんと解脱してるよね!
ということは、
ラーフラが出てくる、第61経、第62経、
そして、この147経を重点的に理解を深めて修法したら、
解脱に近づくということだね!
ブッダがラーフラを解脱させた教えのポイント
六根の『眼耳鼻舌身意』は
変化する『無常』なものなので、
それは、
楽(たのしいもの)ではなく、
『苦』(ドッカ・はかない意味)である。
その、はかない苦であるものを、
『これはわたしのものである、これはわたしである、これはわたしの自我である』
とみなすことは正しいことではない。
自我は正しくない、『無我の教え』
それら、
『無常』で、はかない『苦』のものから、
厭離することで、
解脱することを説いていきます。
かれは、
厭い離れるので、貪りを離れる。
貪りを離れることにより解脱する。
厭い離れる教えは、
第62経「大ラーフラ教誡経」にも出てきていますね!
上にリンクを貼っています!是非見てみて下さい!