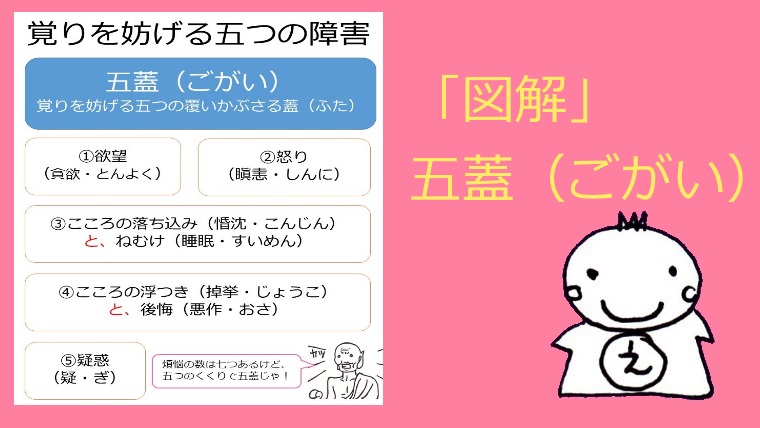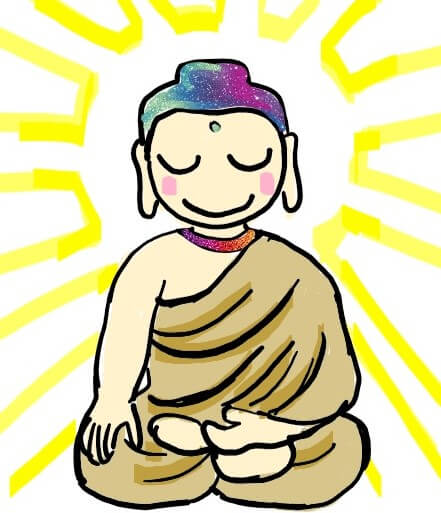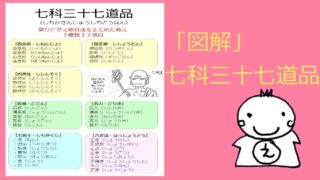五蓋(ごがい)を「図解」で説明します。五蓋とは、①貪欲(とんよく)②瞋恚(しんに)③惛沈(こんじん)・睡眠(すいめん)④掉挙(じょうこ)・悪作(おさ)⑤疑惑(ぎわく)の五つの障害です。覚りの修行の瞑想の邪魔になるので取り除く必要があります。
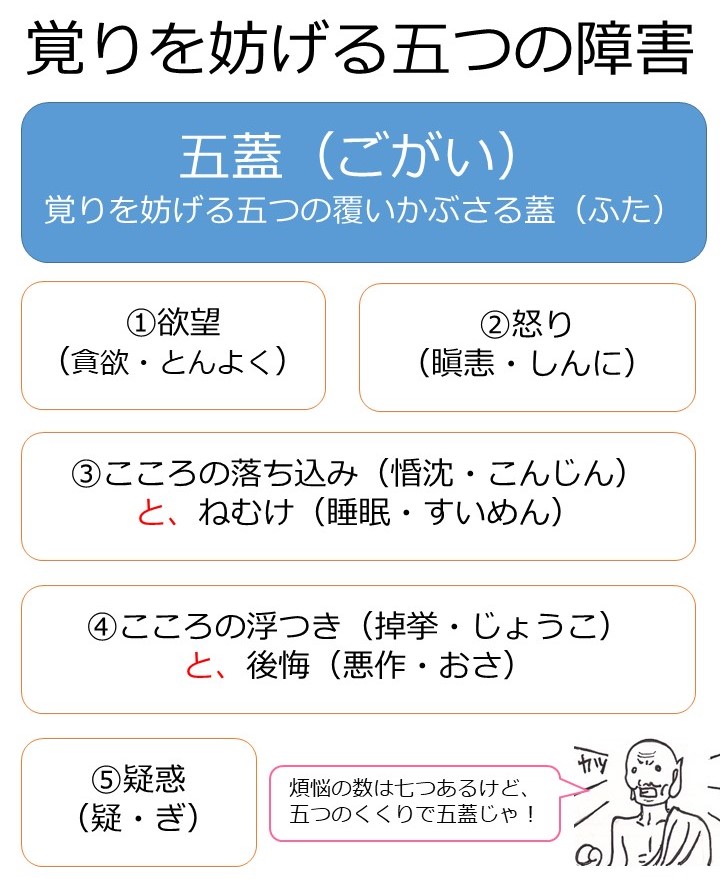
五蓋(ごがい)
五蓋(ごがい)とは、覚りの修行の瞑想の邪魔になる五つの障害です。
五蓋も煩悩のことですが、特に瞑想修行に入るときに邪魔になる五つの煩悩で、
こころに覆いかぶさる”フタ”として表現されています。
瞑想に入る前に取り除く必要があります。
①貪欲(とんよく)
むさぼることです。
常と思う
楽しいと思う
我があると思う
浄らかであると思う
ブッダの真理と真逆の「常楽我浄」、四顛倒(してんどう)に、意を注ぎ、盛んに心を活動させると、貪りのこころが生起してきます。
《貪欲の予防策》
四念処の身受心法で常楽我浄を打破することです。
②瞋恚(しんに)
怒りのことです。
自分にとって邪魔なものに、意を注ぐと怒りが生起します。
《瞋恚の予防法》
慈しみの心と、こころの解脱をもって正しく意を注ぐと、怒りは捨てられます。
③惛沈(こんじん)・睡眠(すいめん)
こころの落ち込みとねむけのことです。
不快なこと、不満や苦痛に不正に意を注ぐと、こころの落ち込みと眠けが生起します。身体がだるく、あくびがでて、身は曲がり、まどろみ、こころが退縮(たいしゅく)します。
《次の六つが惛沈・睡眠の予防策》
①過食をやめる
②行往坐臥の姿勢を正す
③光明への想いに意を注ぐ
④野外に住む
⑤友が善友である
⑥適切な話(頭陀(ずだ)支の話)
*頭陀とは、(原意:払い落とす、棄捨)で、仏教の僧侶が衣食住に関する貪欲(どんよく)を払いのけて仏道修行にはげむこと。頭陀行、乞食の行)のこと
④掉挙(じょうこ)・悪作(おさ)
こころの浮つきと後悔(こうかい)のことです。
心を静めない物事に不正に意を注ぐと、心の浮つきと、後悔が生起します。
《掉挙・悪作の予防策》
精神統一、心の寂静に正しく意を注ぐと捨てられます。
⑤疑惑(ぎわく)
ブッダの教えを疑うこうとです。
疑惑がある思想に、不正に意を注ぐと疑いが生起します。
《疑惑の予防策》
仏法僧に帰依することです。
長部経典22経「大念処」では五蓋を、四正断で観察している教えがでてきます。
「四正断・ししょうだん」(四正勤・ししょうごん)
七科三十七道品の第二番目の行法です。四種の正しい努力を意味します。
四正断を実修すると、精進ができます。
八正道の身口意を正す正精進も、この四正断に収まります。
・律儀断(りつぎだん)
「まだ生じていない不善(悪)を生じさせない」ことです。
・断断(だんだん)
「すでに生じた不善(悪)を捨てる」ことです。
・随護断(ずいごだん)
「まだ生じていない善を生じさせる」ことです。
・修断 (しゅうだん)
「すでに生じた善を増大させる」ことです。
この四正断を念いながら五蓋を取り除き、法を観察して瞑想を精進していく瞑想が「大念処経」にでています。
②怒りもなくし、すべての生き物に思いやりをもち、
③落ち込みと眠けをなくすと、光明が想起できて、注意力をたもった明瞭な意識になり、
④心の浮つきと後悔をなくすと、こころが落ち着き、こころが静かになる、
⑤疑いをなくし、正善な教えでこころが清らかになるのです。
五つの障害の”フタ”を取り除くと、満悦(まんえつ)が生じて、身体が軽安(きょうあん)となり福楽(ふくらく)を感じますよ。
沙門果経より、
《障害の除去・五蓋の除去》
悪意と怒りを捨て、悪意のない心をもって生活し、すべての生き物に思いやりの気持ちをもって、悪意と怒りから心を浄めます。
沈鬱と眠気を捨て、沈鬱と眠気から離れて生活し、光明を想起し、注意力と明瞭な意識を身につけ、沈鬱と眠気から心を浄めます。心の浮動と後悔を捨て、落ち着いて生活し、内に平静な心を持つ者は、心の浮動と後悔から心を浄めます。疑うことを捨て、疑いを脱して生活し、もろもろの正善なる教えに対する疑いのない者は、疑いから心を浄めます。



(参考:「図解」ブッダの教えもくじはこちら)