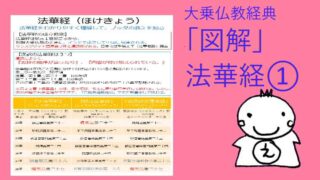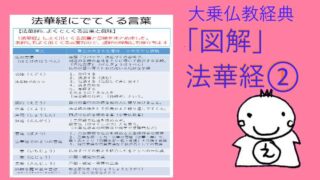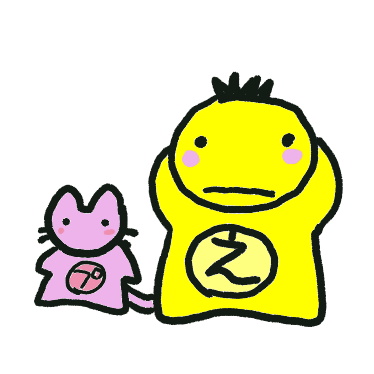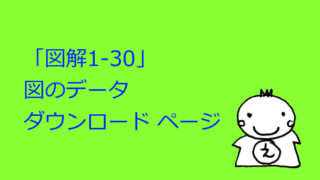この法華経(ほけきょう)「序品第一」(じょほんだいいち)ほぐし読みは、「大乗仏教」の妙法蓮華経を、大まかにほぐし読みに整理しました。法華経「図解①」.法華経「図解②」と照らし合わせてみて下さい。
法華経(ほけきょう)「序品第一」(じょほんだいいち)ほぐし読み
第一章「序品第一」(じょほんだいいち)
《霊鷲山でブッダとみんなが集まる》

ブッダは霊鷲山にいました。
たくさんの弟子や天の神々も世尊の説法を聞こうと周りにいます。
ブッダは「大乗経の無量義」を説きました。
「大乗経の無量義」とは、一般的に法華三部経のうちの無量義経(むりょうぎきょう)と解説されています。
法華三部経は、
1、無量義経(むりょうぎこう)、この妙法蓮華経を説く直前に説いた、「無量義」限りない意味を持ったお経。妙法蓮華経を読む前に読む「開経」(かいきょう)と呼ばれる。
2、妙法蓮華経(みょうほうれんげきょう)、略して法華経(ほけきょう)と呼ばれる。
3、観普賢菩薩行法経(かんふげんぼさつぎょうほうきょう)、妙法蓮華経の最後第二十八章の「普賢菩薩勧発品」のあとを受けて、普賢菩薩が主役で、徹底した懺悔(ざんげ)が説かれているので「懺悔経」(ざんげきょう)とも呼ばれ、また結びの経典でもあるので「結経」(けつきょう)とも呼ばれる。
そのあと、
「無量義処三昧」(むぎょうぎしょざんまい)の瞑想の境地に入ります。
「無量義処三昧」(むぎょうぎしょざんまい)の瞑想は
法華経を説くに先だって入った禅定の境地。
「実相三昧」(じっそうざんまい)「無相三昧」(むそうざんまい)とも呼ばれる。
無量義処は無量に分別されるもとの基礎の教え。
三乗を区別する教法の根底の、諸法の実相と解説される。
その諸法の実相をこころに専念する状態が無量義処三昧と解説される。
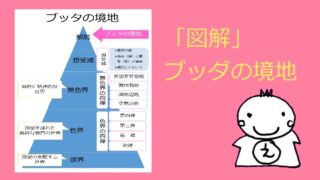
そして、いきなりブッダは、
《光を放つブッダ》

つぎに、ブッダは
眉間(みけん)の白毫(びゃくごう)から光を放って、東の方の地獄から天界にいたるまで、照らしました。
その光の中なかには六道輪廻のあらゆる世界をみることができました。
仏の清らかな世界も数多くみられ、出家者も在家者も修行するすがたや、
仏舎利塔を築いているすがたも見ることができました。
光を放つと天界から花が降りそそぎ、地は清められ、誰もが心身ともに、これまで経験したことがない清々しさを感じています。
その情景を見ていた弥勒菩薩が
「なぜ世尊は光を放ったのだろうか?」と疑問をもちました。
弥勒菩薩は、世尊はすでに仏法を明らかにして、人々を悟りの道に導いているのを見てきたのでした。
ある修行僧は布施の修行を行い、独り静かに読経する者や、山に入り禅定をする修行僧もいます。
菩薩の道をゆく求道者は、地獄に堕ちたものでさえ救いだし仏道に導く者もいます。
仏の子である求道者は、忍辱の力を身につけ、罵りからも耐えて仏道を求めます。
仏の入滅後、仏舎利塔に祈りを捧げる者もいました。
《弥勒菩薩は文殊菩薩に光を放った理由をきく》
ブッダが光を放った理由を文殊菩薩に聞きました。
文殊菩薩は答えます。
「ブッダはこれから、大いなる法を説こうとされています。過去にもおなじような風景を見たことがあります。」
《過去仏のときのエピソード》
過去の仏、日月燈明(にちがつとうみょう)のときには、
説かれた法をたよりにする修行僧(声聞)には、
「苦を脱する四つの真理の四諦(したい)を説きました。」
縁起の法則を頼りにする修行僧(縁覚)には、
「十二因縁を説き示しました。」
菩薩の道を求める修行者(菩薩)には、
「布施・智慧などの六波羅蜜を説きました。」
■声聞・縁覚・菩薩の違い
「声聞」(しょうもん)は四諦で仏道を修める者(小乗仏教者)
「縁覚」(えんがく)は十二因縁で仏道を修める者。辟支仏(びゃくしぶつ)とも言う。(小乗仏教者の阿羅漢や婆羅門)
「菩薩」(ぼさつ)は六波羅蜜によって仏道を修める者(主に大乗仏教者)
※ちなみに、サンスクリット語訳には声聞と、偉大な志をもつ求法者の二者で訳されています。
この日月燈明が入滅すると、次の日月燈明が世に出現して、その次、その次と繰り返し出現してきました。
そして最後の日月燈明のときに、
眉間の白毫から光を東に放ったのです、
そして、菩薩の道を行く修行者の妙光(みょうこう)に
「妙法蓮華経」を説き示したのです。
この妙法蓮華経は、大乗の正しい教えの白蓮であり、菩薩を導く法であり、諸仏に護念された経典で、
このお経をとき終えると、
日月燈明はこういいました。
「諸法の実相は、すでに語った。わたしは今夜入滅して、完全な涅槃に入る。皆は気ままな放逸(ほういつ)を離れよ。」
日月燈明の入滅後は、妙光菩薩が妙法蓮華経を保持して説き広めました。
しかし、妙光の800人の弟子の中に、求名(ぐみょう)という、怠け心があり、名声に執着する修行者でしたが、
その怠け者の求名も菩薩の道である六波羅蜜をすすみ、全き者となりました。
過去の妙光菩薩は、今の文殊菩薩です。
そして、過去の求名が、今の弥勒菩薩なのです。
そして、今まさに世尊が光を放ったのは、かつての瑞兆です。この世において、大乗の正しい経典を説き示すでしょう。疑いの心があっても、その疑念は除き断たれます。
六波羅蜜(ろくはらみつ)で、六つの彼岸に渡る(さとる)方法
1、布施波羅蜜(ふせはらみつ)、布施をすること。
2、持戒波羅蜜(じかいはらみつ)、戒律を保つ。
3、忍辱波羅蜜(にんにくはらみつ)、耐えて他人の迷惑を許す。
4、精進波羅蜜(しょうじんはらみつ)、努力して行う。
5、禅定波羅蜜(ぜんじょうはらみつ)、集中して行う。
6、智慧波羅蜜(ちえはらみつ)、上記5つを修養してえられる智慧。
*法華経の「図解②」に般若波羅蜜多心経も少し加えて解説しています。
《序品第一 終わり》 つづく