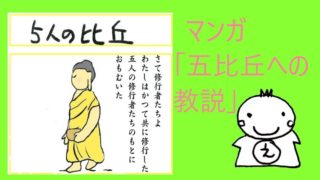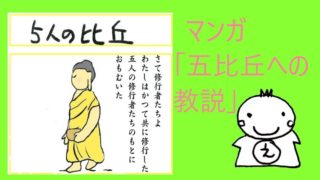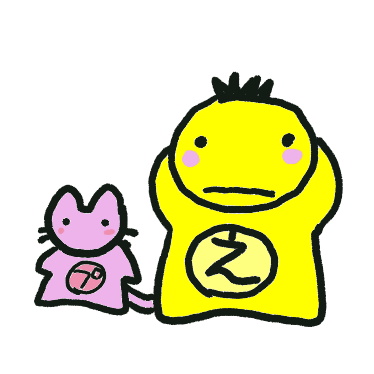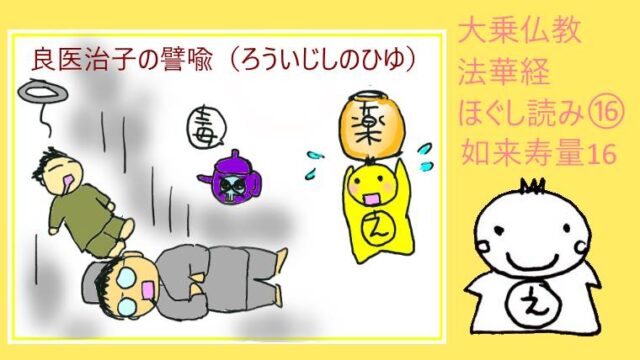この法華経(ほけきょう)「譬喩品第三」(ひゆほんだいさん)ほぐし読みは、「大乗仏教」の妙法蓮華経を、大まかにほぐし読みに整理しました。
法華経「図解①」.法華経「図解②」と照らし合わせてみて下さい。
第2章「方便品第二」(ほうべんぽん)
前回、ブッダは白毫から光を放ち、大乗の正しい経典を説き示すでしょう。で終わりました。

法華経(ほけきょう)「方便品第二」(ほうべんぽん)ほぐし読み
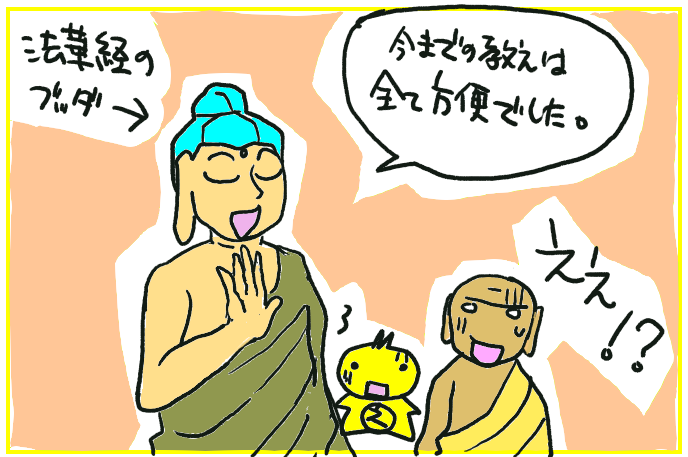
《ブッダはサーリープッタに話します》
仏の智慧は深遠で、見がたく、如来がさとった智慧は、声聞、縁覚の道を行くものが知るところではないのです。
今まで方便を使って人を真理に導いてきましたが、わたしが成就したのは難解の法であり、声聞、縁覚たちには理解しがたいので説くのをやめておきましょう。
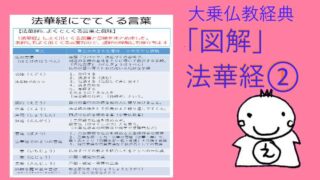
ただ、わたしと仏のみ
相・性・体・力・作・因・縁・果・報・本来究竟等と、
究極においては等しい諸法の実相を見極めているのです。
「十如是」(じゅうにょぜ)
相(そう)・すがた
性(せい)・性質
体(たい)・形
力(りき)・能力
作(さ)・作用
因(いん)・過去の由来
縁(えん)・おかれた状態
果(か)・現在の結果
報(ほう)・未来の在り方
本来究竟等(ほんらいきゅうきょうとう)・すべては究極にあいて等しいさま
※サンスクリット語訳では、「如来はあらゆる現象を知っている。その現象がなにか?どうのようなものか?いかなる本質をもつか?」と訳されていて、具体的な十の要素の用語はでてきまていません。 この十如是は鳩摩羅什訳で足された可能性があるといわれてます。
付け足されたことを知らなかったら、後で見た人はそこが重要と思っちゃうよね。
「十如是」は、中国天台宗開祖智顗によって教義が展開して、三つの真理が融合している意味と解説もされています。
■空諦(くうたい)・空の真理。すべては不変の実体をもたない意味
■仮諦(けたい)・仮の現れとしての真実。すべて空であっても生起する物事がある意味
■中諦(ちゅうたい)・中道の真理。現実は空諦と仮諦のどちらにも偏らずにある意味
原始仏典の四諦とちがう教義の展開になっているね。




声聞、縁覚、阿羅漢でも、法の深遠を知ることはできないのです。
しかし、わたしや仏は人々を苦から引き出すために、
方便の力で三乗の教えを説いてきたのです。
【方便の力】
方便・・・原語「ウパーヤ」は近づくの意味で、
到達の手段の意味さとりに導いて救済する手段。
《サーリプッタや他の者たちが疑念をもつ》
これを聞いた、サーリープッタや他の者たちは、ブッダに疑念を持ち、聞きました。
「なぜ方便を讃えて、真実を知ることができないと語るのですか?どうか悟りに至る道をお聞かせ下さい。」
ブッダは答えます。
「いえ、説くのは辞めておきましょう。語れば神々も人も驚き疑いの心を増やすでしょう。」
サーリープッタは三度お願いを求めました。
ブッダは答えます。
「わかりました。これからあなたたちに、言葉を選んで語り聞かせます。」
この時、増上慢におちいっている、出家と在家の5千人が立ち去ります。
諸仏は知見を示し、悟らせ、道に行かせる、一大事の因縁(人々に仏の知見の一切種智を示して、人々をさとらせる)のために、この世に表れるのです。
仏は一仏乗を説くのであって、
声聞・縁覚の二乗
声聞・縁覚・菩薩の三乗とかを説くのではありません。
方便の力をもって、一仏乗(声聞・縁覚・菩薩すべて合わせた教え)の一切種智に導くためなのです。
人々が貪瞋痴に犯されているので、方便の力で三乗を説くのです。
【一仏乗】(いちぶつじょう)
声聞(四諦の教え)・縁覚(十二因縁の教え)・菩薩(六波羅蜜)のすべての教えを統合したさとりへの乗り物の教え
しかし、声聞、縁覚に満足して阿耨多羅三藐三菩提(無上の真実の完全なさとり)を求めないならば、その人は増上慢ゆえに真理の道から外れているのです。
小さな法を求めて、深くて神秘な道に入れない人がいるので、
わたしは大乗を説きます。誰かを救いたくないという想いはありません。救いを惜しむことはありません。
苦悩を滅する涅槃の道をしめしましたが、
真実において諸法はもとより無上のさとりにあるのです。
無上の法を大一義に導きます。
仏が入滅したら、仏舎利を建てて、仏像をつくり、心から祈りなさい。
《法華経での初転法輪》
初転法輪のエピソードを説きます。
「世尊よ。ウパーヤ(方便の力)を発動して、生きとし生けるもののために三乗を説きたまえ。」と十方の諸仏の声を聞きました。
そして、
五比丘には生老の苦を滅する涅槃を説いて、阿羅漢の境地に引き上げました。
いま、方便をすてて、無上道をときます。
サーリープッタよ
仏の言葉の方便を聞いて心に喜びをもち、祈りを捧げるならば、
それは三世諸仏の一切に及びます。そしてみずから仏になることができるのです。
疑念を捨て去り、仏をめざしなさい。
《方便品第二 おわり》 つづく