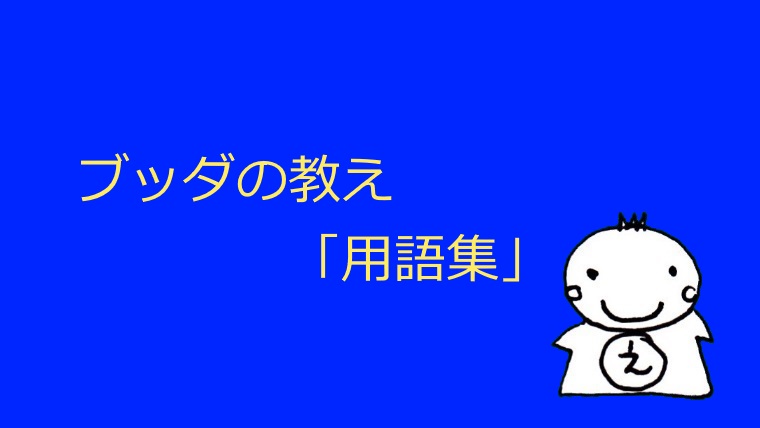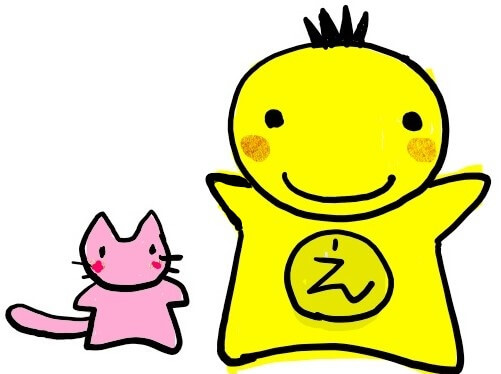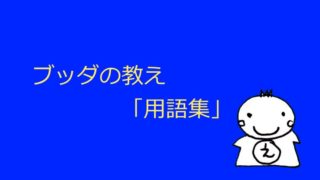五禅支(ごぜんし)とは「尋・伺・喜悦・楽・一境性」の五つの「支」でこころの精神作用です。色界(しきかい)の四禅(しぜん)を始めたときに存在する心の境地です。
目次 クリックでジャンプ
五禅支(ごぜんし)
五禅支(ごぜんし)とは「尋(じん)・伺(し)・喜悦(きえつ)・楽(らく)・一境性(いっきょうせい)」の五つの「支」で、こころの精神作用です。
・「尋・じん」
大まかな考察の意味で、瞑想して考察を始めた初期の状態です。
・「伺・し」
細かな思慮の意味で、瞑想して考察を継続してる状態です。
・「喜悦・きえつ」
瞑想で欲を離れることで得られる「喜び」です。
・「楽・らく」
瞑想で得られる安楽(あんらく)です。
・「一境性・いっきょうせい」
集中する気持ちのことです。

五禅支を手放す瞑想が「四禅」(しぜん)
「五禅支」の心理作用をひとつずつ、手放していく瞑想が原始仏典によくでてくる「四禅」(しぜん)の瞑想になります。漢訳では四静慮(しじょうりょ)です。仏教の世界観「三界」(さんがい)の色界の瞑想になります。
「四禅」は第1経「梵網経」(ぼんもうきょう)にもでてきます。
原始仏典 長部経典 第一経「梵網経・ぼんもうきょう」には
「現法涅槃論・げんぽうねはんろん」現世において初禅から四禅に達して住する、
「如来自ら覚り体現して教示している。賢者だけが理解できる諸法」
と説明されてでてきます。
(参考:「用語集」もくじはこちら)