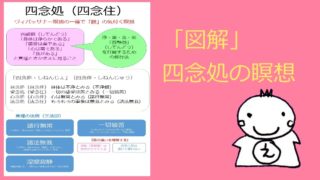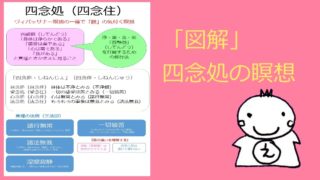この「大日経」(だいにちきょう)悉知出現品第六(しっちしゅつげんほん)は、角川文庫「全品現代語訳 大日経」著者:大角修先生の本を主に参考にして、ほぐし読みにしました。
「阿字観の教説↓」と照らし合わせてみて下さい。

前回、大日如来は、金剛薩埵の三番目の質問の回答と
「月輪観」も告げました↓。上↑と絵が同じだけど違うページですよ!

目次 クリックでジャンプ
阿字観・心月輪の瞑想の教説「大日経」悉知出現品第六(しっちしゅつげんほん)
悉知出現品第六(しっちしゅつげんほん)
大日如来が決定智円満の法句を説きます。
大日如来は三世無量の門において、決定智円満の法句を説きました。
真言を修して菩薩の道をゆく者は、速やかに真言の悉知(成就)を得られるでしょう。
曼荼羅をみて、尊に印可(いんか・承認)せられ(手に契印をすることかと思いますが不明です。)、
真言を成就して、菩提心をおこせば、深く信じて、慈悲あり、欲深い樫悋(けんりん)はない。
など、二十の成就が説かれます。
そして、真言を唱えました。
なうまくさらばたた ぎやていびゅ びじんば ぼつけいびゃく さばた ああ あんあく
(一切の如来に帰依してたてまつる。一切法と時に修行・菩提・涅槃へ)
次に、
大日如来は心月輪の瞑想を説きます。
大日如来は心月輪(しんがちりん)の瞑想を説きます。
鏡曼荼羅(きょうまんだら)の大蓮華王座において大日如来を深く三昧に住すれば、
光明に包まれた大日如来があるのです。
妄執と分別を離れて、静かに思惟し念誦するのです。
この部分は、
心月輪(しんがちりん)のことで、
本尊を自分の胸に観ずることと解説されています。
この心月輪(しんがちりん)を、
一か月に10万回満たすのです。「41.歓喜地」
そして、翌月には、
諸尊に塗香や花を捧げて、衆生類を饒益(利益)するのです。「42.離垢地から47.遠行地」
三か月目には、
諸々の利養は捨棄しなさい。
瑜伽の瞑想において思惟自在となり、
衆生に一切の障礙なく安楽であらんことを願って
苦悩の毒を除き、
餓鬼にも飲食を満足させて、
地獄の苦も除滅しなさい。「48.不動地から50.法雲地」
上記の「」と対応している「菩薩の修行52段階」の、
『十地の段階の修行』
50 法雲地(ほううんじ)
49 善想地(ぜんそうじ)
48 不動地(ふどうじ)
47 遠行地(おんぎょうじ)
46 現前地(げんぜんじ)
45 難勝地(なんしょうじ)
44 焔光地(えんこうじ)
43 発光地(はっこうじ)
42 離垢地(りくじ)
41 歓喜地(かんきじ)は浄菩提心と同じ

そして、
自己の功徳の力
如来の加持の力
法界の力
の三つの加持の句によって心に真言を誦持しなさい。
と、
大日如来は真言を唱えます。
なうまくさらばたた ぎやていびゅ びじんば ぼつけいびゃく さばた
けん うどぎゃていそは らけいまん じゃじゃなうけん そわか
(一切の如来に帰依してたてまつる。一切法と一切時と空に、進行し、震動し、水・虚空・空)
そして、
さらに伝えます。
行者は満月の夜に真言を誦しなさい。
障礙(しょうげ)は伏せられ、心に迷乱はなくなるでしょう。
因も空なれば、果もなし。
まさに知るべし、
真言の因業を離れたものであることを。
無相の三昧(ざんまい)の三摩地(さんまじ)において悉地(しっち・成就の意味)は心に生ずるでしょう。
そのとき、大日如来は
四魔(煩悩・五蘊・死・天)を降伏する金剛の真言を説きました。
なうまくさまんだぼだなん あびらうんけん
南麼三曼多勃駄喃 阿毘羅吽欠
(尽十方の諸仏に帰依してたてまつる。地・水・火・風・空)
あびらうんけん!
は、よく聞くよね!
五蘊はこちら↓


そして、
次に大日如来は阿字観を説きます。
大日如来は阿字観(あじかん)を説きます。
阿字は最勝の大因陀羅輪(だいいんだらりん・地輪=大地)である。
真言の法門において菩薩の道をゆく修行者は
阿字を自身とし、内外ことごとく同等としなさい。
貪瞋痴を離し、清浄を得よ。
坐して、阿字を観じ、
それが耳根にあると想い、
念持して一か月を満たせば耳根清浄を得ることができるでしょう。
一切衆生の心に随順して、
ことごとく歓喜せしめよ。
如来が悉地を授けるのは真言行より発生するのです。
まさに成就を作せ。
《悉知出現品第六(しっちしゅつげんほん)終わり》つづく
ぼーさん、阿字観上手にできました~♪
すごいね!えん坊!
また、心月輪も挑戦してね!(笑)
密教の「阿字観」の瞑想も「貪瞋痴」を手放す
真言の「あびらうんけん」などが、
強く印象に残る密教ですが、
前回の「金剛薩埵の三つの質問」の回答も「障礙や畏れを取り除く」など、
よく読むと、
やはり、
自己のこころを観察して、自己の中の悪い煩悩「貪・瞋・痴」を
手離していくことが教えられているのがわかります。
原始仏典でよく出てくる瞑想も載せておきます。参考ください!